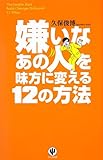出版企画を出版社に売り込んで採用されたら、次は原稿の執筆です。
しかし、本の原稿を執筆するときに、なれていないと手が止まることもしばしば…。
息抜きをしながら執筆していると、ついつい原稿が脱線してしまい、なかなか上手くまとまらないことも。
執筆しながらも他のコトや新しいコトなどが思いついたりして、話しの流れがどんどんおかし方向に進んでしまったり、、一貫した話しにブレが…。
こんな人たちのために、一番、簡単な原稿の書き方を書いておきます。
この方法は、縦書きだろうと、横書きだろうと関係ありません。
では、早速。
まず、企画書に書いた構成案(目次案)をエクセルにコピペします。
構成案(目次案)もは、章構成から節構成ぐらいまでは書いてあるはずです。
なので、章と節をエクセルの列をずらして、階層構造になるようにしてください。
そしたら、今度は節の下の階層としてさらに列を追加して、その節で説明したいことを箇条書きで構わないので、どんどん書き足していきます。
箇条書きは、執筆期間中に思いついたら、ドンドン書き足してもらって構いません。
箇条書きは多い方が、次の行程が楽になりますので、毎日のように階層構造を見直しながら、思いついたらドンドン追加していきましょう。
それが終わったら、全体を俯瞰して見てみてください。
内容の重複はないか、辻褄が合っていない箇所はないか、話しの流れはスムーズか…前後関係を見ながらチェックをしてみてください。
あとは類書やウェブの内容などもチェックしつつ、内容に過不足ないかも確認しましょう。
あとは、その節ごとに箇条書きを見ながら本文を書いていきます。
書く内容と節ごとのだいたいの文字数が分かれば、あとはどう説明したら、その文字数でそれらのことを伝えられるかを考えて書くだけです。
この作業の流れは、簡単に言えば、構成案(目次案)を肉付けしていきながら、一冊の書籍に仕上げていく作業です。
実は、テキストファイルで原稿を書くと前後関係が把握しづらくなるため、話しの流れが見えにくくなるのです。
その点、この方法だと、各項目を階層構造にすることで、全体を俯瞰して見ることができます。
そして、新たに追加したい内容についても、階層構造から最適な場所に付け加えることも可能なのです。
この方法は、はじめて執筆される人でも簡単に原稿を書くことができる方法です。
さらに階層を増やし、セルの設定を変更して文章を入力できるようにして、そのまま本文を書く進める著者さんもいらっしゃいます。
その場合、執筆終了後にテキストファイルにコンバートする必要がありますが、もし、エクセルの方が作業がしやすいという人は、是非、やってみてください。
やってみると分かるのですが、ワードなんかより、全然、使いやすいですよ。